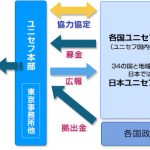介護タクシーは名前に介護と含まれるように、介護に関わる輸送サービスのことで、主に要介護者や体に不自由を抱えている人が利用できます。
一般のタクシーと異なるのは、利用可能な対象者が決まっているのと、車両がセダンではなくワンボックスカーが主流な点が挙げられます。
ワンボックスカーが主流の理由は明確で、それは車椅子に座った状態や、ストレッチャーで運ばれた状態で利用者が乗車することにあります。
この為、必然的にセダンでは対応できず、より大きなワンボックスカーが活用されているわけです。
ワンボックスカーなので乗り降りの際に近所に目立ちますが、派手な車が乗り付けることはないので、その点は心配しなくても大丈夫です。
車両の外観は特殊なものではなく、市販車に屋号のステッカーが貼られている程度ですから、一見しただけではタクシーと分からないこともあります。
介護タクシーは市販のワンボックスカーが主な車両
このように、介護タクシーは市販のワンボックスカーが主な車両で、車椅子やストレッチャーでの乗車が前提となっているのが特徴です。
車椅子の人がセダンに乗ろうとすると、乗り降りに時間を要したり車椅子を積み込む手間がありますが、ワンボックスカーならそのままスムーズに乗り降りできるので楽です。
これなら無理な姿勢で体に負担を掛ける心配もなく、快適に外出することができます。
介護タクシーの運転手は、車の運転の他にも乗り降りの介助のサービスを提供しており、そこが一般のタクシーと大きく違います。
介助サービスのないタクシーは福祉タクシーと呼ばれて区別されていますから、利用の際には混同したり間違えて選ばないように気をつけましょう。
福祉タクシーは介護保険の対象外で全額負担が原則
ちなみに福祉タクシーは介護保険の対象外で全額負担が原則ですが、同乗者の乗車は認められているので家族などの付き添いの人が一緒に利用できます。
逆に介護タクシーは家族の同乗が認められていないので、乗り降りも移動も運転手に任せることが必要です。
ところが病院内の移動の介助はサービスの対象外ですから、病院に到着したら看護師にバトンタッチする形となります。
位置づけが通院等乗降介助なので、通院を目的とする利用が多いですし、補聴器や眼鏡の製作で利用されることもあります。
つまり、病院に限らず本人が外出して出向く必要がある場合に、介助を必要とするタクシーの利用が行えるわけです。
補聴器や眼鏡の購入を目的とした外出も、介護保険の適用が認められていますから、料金の負担を気にせずに安心して使うことができます。
選挙の投票で投票所に出向いたり、預貯金の引き出しや手続きの為に銀行に行かなくてはいけない、こういうケースも介護保険適用で利用可能です。
役所に書類を提出したり受け取る場合も同様ですが、外出ついでに飲食店に足を運んだり、ドライブ代わりに遠回りして帰るなどはできないです。
長距離を長時間となれば費用も高額になるのでよく考えて選ぶべき
介護保険を使わないのであれば、用途に限定されず全額自己負担で介護タクシーを利用できますが、長距離を長時間となれば費用も高額になるのでよく考えて選ぶべきです。
介護タクシーの利用が認められているのは要介護認定1以上の人で、要支援1から2の人は対象外です。
しかし、要介護1でも自力で車両に乗り降りできる場合は、介護保険を使ってタクシーを利用できないばかりかサービス自体の利用が不可能となります。
要介護認定を受けていても介助が必要かどうかで利用の可否が決まりますから、その点は非常に厳格です。
それから街中で車両が拾えたり電話1本できてくれるわけではなく、ケアプランに組み込む形で事前に利用計画を立てる必要があります。
事業者の選定はケアマネジャーが相談に乗りますが、利用の開始は利用者と事業者の間で契約を結んでからです。
基本的な介助以外のサービスについては着替えや靴を履く介助、病院での受付や会計、薬の受け取りなどが利用者に合わせて提供されます。
ただし、これらの付随する介助もケアプランに組み込む必要があるので、ケアプランにないサービスを運転手に求めることは不可能です。
目的地も外出のスケジュールも全てケアプラン通りに実行されますから、目的地を変更したりその都度追加のサービスを利用することはできないです。
まとめ
タクシーといっても、利用に関する自由度が低く利用者の思い通りにはならないので、わがままは聞いてもらえないことに注意です。
車両は乗り降りに使うリフトやスロープを備えており、効率良く乗り込めたり体に負担が掛からないように配慮されているので快適です。
追加料金を負担することで車椅子やストレッチャー、酸素吸入セットを借りることができますが、どの介護器具のレンタルが行われているかは事業者によります。
乗り降りできる場所は自宅や有料老人ホーム、サ高住やケアハウスなど生活している居住地に限られるので、ここにも利用における制約があります。
最終更新日 2025年12月15日 by wannya